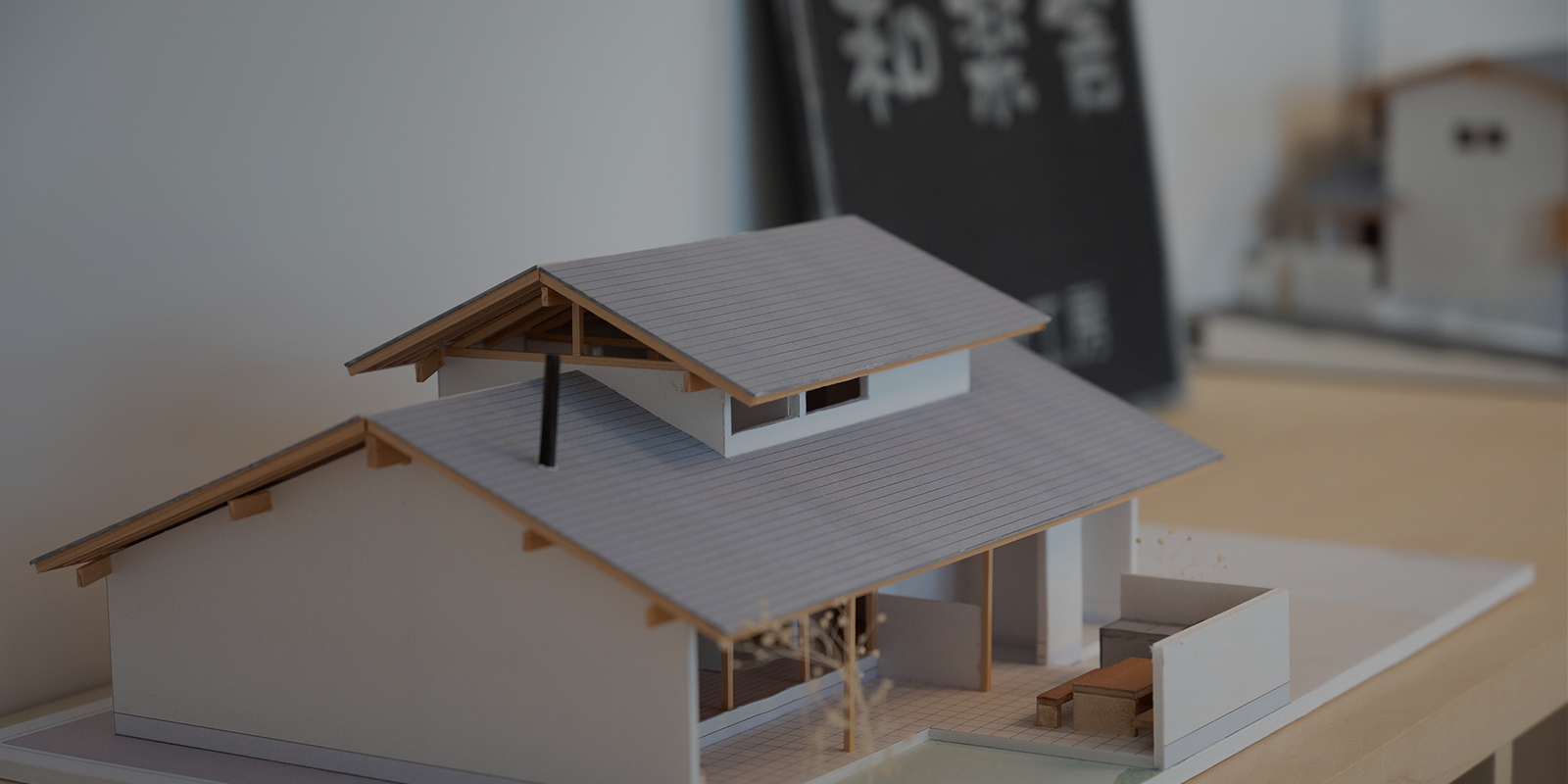こんにちは、スタッフ初瀬です。
今年もあと残すところ半月となりました。
浜松市も寒さが厳しくなってきましたね。
先日ついに積算士試験の申し込みを完了させました!
恥ずかしながら、去年も受けようと思いつつ
二級建築士合格に浮かれていたせいか
気づいたときにはもう遅かったのです。
積算士は民間資格で、合格率は60%前後程。
積算とは、日常ではあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが
簡単にいうと工事金額を算定する仕事です。
買い物をするとき、まず価格が気になりますよね。
積算士は、建物工事にかかるすべての数量を算出します。
数量を間違えてしまったら、合計金額に影響を与えるため
当たり前ですが、きちんと算出しなければなりません。
設計図が完成し、図面に記載された寸法等から算出します。
図面の読解力や、今後図面に記載したほうが良い事項などに気づくことができるので、
自分自身、積算の仕事はとても力になるなあと思っています。
新築となれば、基礎、柱や梁、屋根材の材料費はもちろんのこと、
それから地面を掘ったり埋め戻したりする労務費まで
工事の流れ、時期を考慮し工事費を算出します。
工種ごとに算出する必要があるため、
各工種の工事内容を適切に把握する必要があります。
和楽舎設計工房での業務の中でも、浜松市の物件は毎回積算をします。
工事内容から、無駄がなく品質・耐久性が良いものをと設計していますが、
数量算出についても間違いがなく、余分なお金が発生しないよう注意しています。
お客様に適切な価格で良い建物をつくるために
あまりメジャーではないのかもしれませんがとても重要な業務内容だと感じております。
(▲私が高校時代から勉強しているテキスト)
この試験を機にさらに知識が付き、
日頃の業務に還元できることをやりがいに感じます。
試験は年明けとなりますが、あと少し頑張ろうと思います。
スタッフ初瀬
【works(浜松 磐田)】
【top】