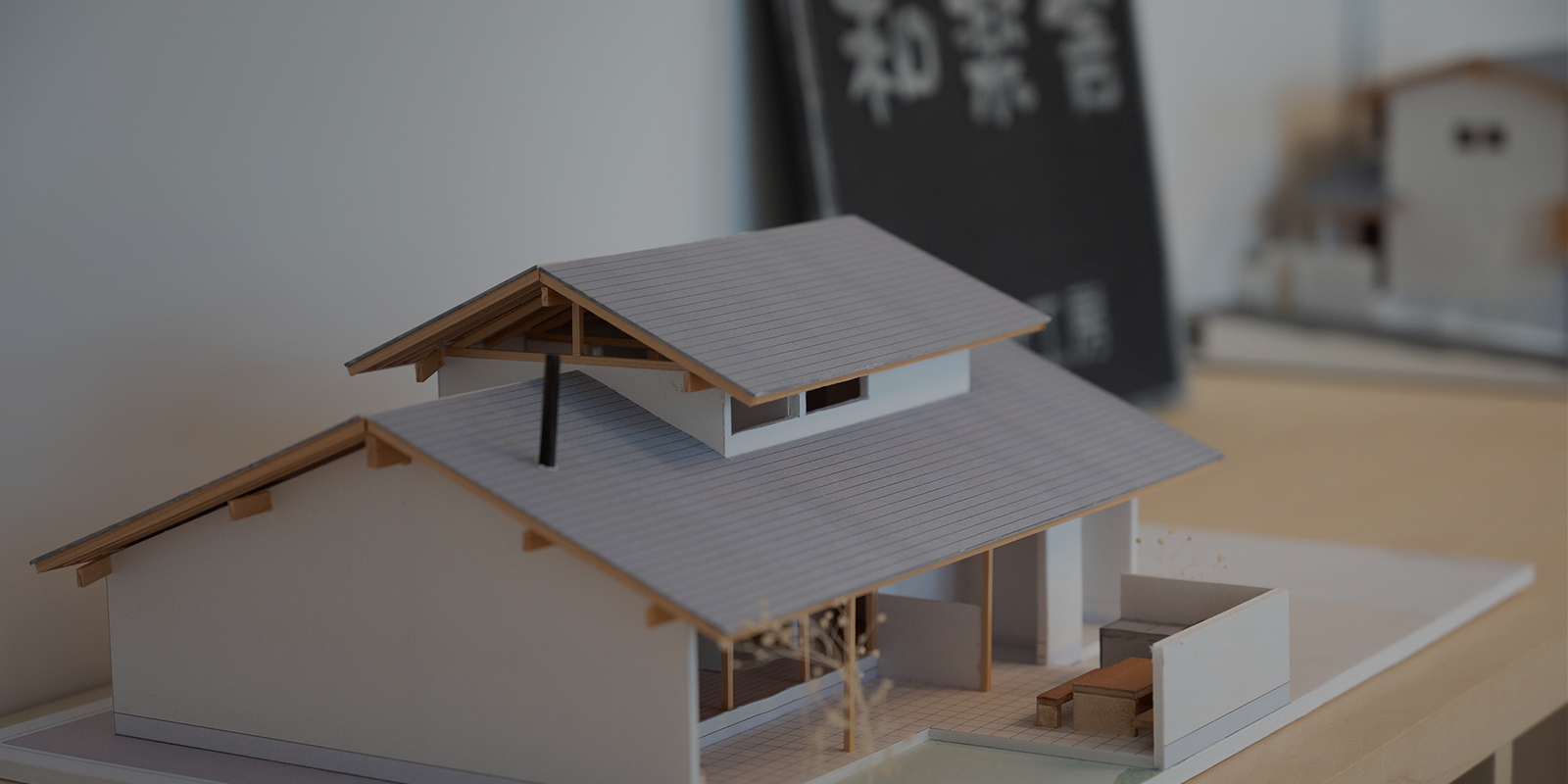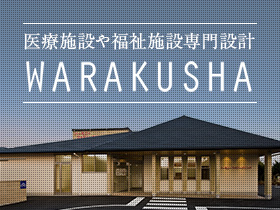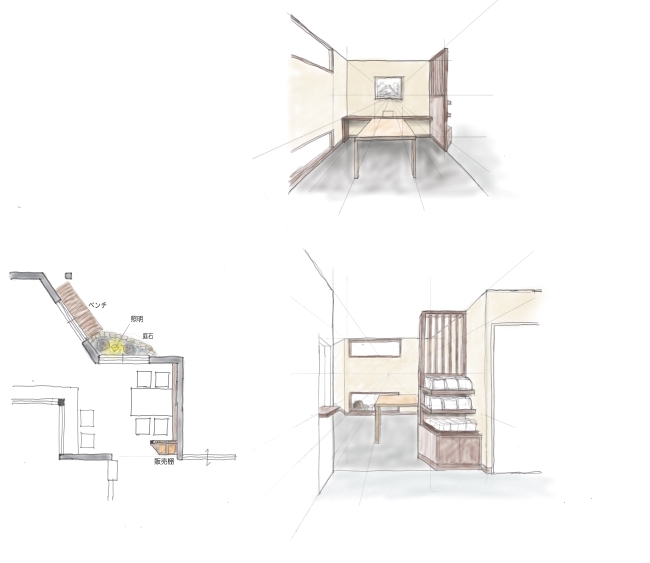こんにちは。
スタッフ 里沙です。
本日は、中区・曳馬にある家具屋さん
【エルムコート様】にて開催の展示会
に行ってきました。
会場は、ヴィンテージのペルシャ絨毯をはじめ、
ギャッベや緞通など、産地もテイストも様々な絨毯が揃う圧巻の空間。
たとえばペルシャ絨毯だけでも、
手工業の最盛期で職人の腕もずば抜けていた
1979年イラン革命以前の手織りの作品が、
美術展さながらに並べられています。
ペルシャ絨毯というと、
ヨーロッパ各国の王室などをイメージされる方も多いかもしれません。
しかし実際には産地や時代により色柄のバリエーションが広く、
ブルー系やモノトーン、直線的な幾何学模様のものなども、
それはそれは美しいのです。
和室やシンプルモダンのインテリアにもしっくり馴染むものが
豊富にあることを、今回改めて実感しました。
様々な建築とのマッチングの可能性を、
今後追求してみたいと思います。
今回、主催のリビングサンアイ様よりご案内いただき
素敵な機会を得ました。ありがとうございます♪
開催は、明日11月29日(月)まで。
ご興味のある方は、ぜひ会場まで足をお運びくださいね!
(スタッフ:里沙)
【works(浜松 磐田)】
【top】