クリニック設計専門サイトにて、
「工事監理」についての記事を掲載しました。
設計に比べ認知度の低い業務ですが、
ていねいな「監理」は
お施主様にとって
1.建築基準法の要件を満たす
2.建物の価値がさらに高まる
3.実際の建物を前に最終確認できる
という3つのメリットがあります。
ぜひ、ご一読ください!
コラム
(↓クリックするとページへ移動します)
クリニック新築の流れ【第3回:「ていねいな監理」がもたらす3つのメリット】
メディア掲載
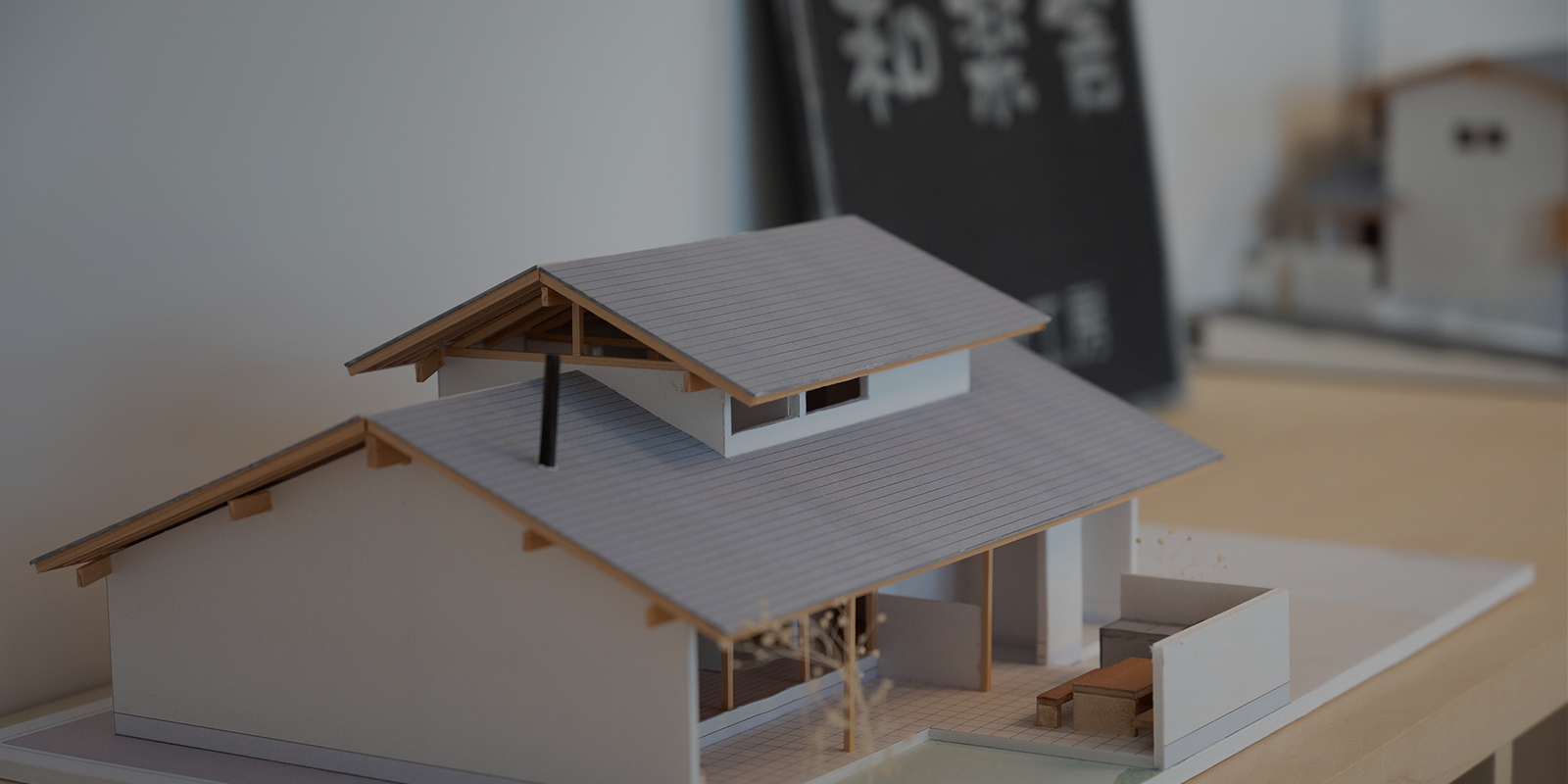

2021/05/17
|
ニュース
クリニック設計専門サイトにて、
「工事監理」についての記事を掲載しました。
設計に比べ認知度の低い業務ですが、
ていねいな「監理」は
お施主様にとって
1.建築基準法の要件を満たす
2.建物の価値がさらに高まる
3.実際の建物を前に最終確認できる
という3つのメリットがあります。
ぜひ、ご一読ください!
コラム
(↓クリックするとページへ移動します)
クリニック新築の流れ【第3回:「ていねいな監理」がもたらす3つのメリット】
メディア掲載
2021/05/14
|
2021/05/09
|
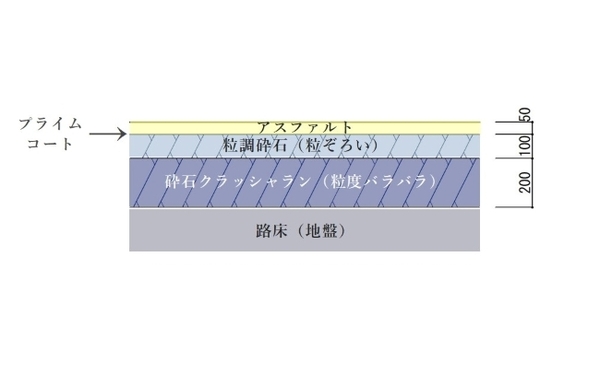
2021/04/16
|
ニュース
和楽舎設計工房の医療福祉施設専門サイト
「WARAKUSHA」の取り組みを、
静岡新聞さんに採り上げていただきました!
4/15(木)夕刊 第一面に、写真付きにて。
医療福祉専門サイトを開設した経緯や
サイト内で展開しているコラム等について
取材いただきました。
こちらからネット記事もご覧いただけます。
ぜひ、ご覧くださいませ。
(タイトルをクリックすると記事ページへ移動します)
↓
「コロナ禍 建築に新需要 静岡県内設計事務所など、細やかさで勝負」
WAKARUSHAサイトが皆様にお役立ていただけるよう、今後ますます育てていく所存です。
今後ともよろしくお願い致します!
2021/04/16
|
こんにちは、スタッフ初瀬です。
(^^)/
先月から、母校の放課後児童会施設整備工事の設計が始まりました。
以前にも、体育館の外壁改修の設計に携わることができましたが、
また母校の設計が出来ることとても嬉しく思います。
まず配置計画から。
配置計画には、配慮する点が多くあります。
何を優先に考えるかで、いくつかのプランが出来上がり、
それぞれのメリット・デメリットをまとめます。
建築基準法の制限、施設利用者の動線、景観条例、
既存のものの解体を最小にするなど、、
様々な観点から、プランを選定します。
使い勝手を優先したばっかりに、景観が乱れたり、
景観を尊重したばっかりに、施設利用者の安全が確保されないプランになったり、
偏ることがないように検討。。
まずは、おおよその寸法を抑えた配置計画、
次に、細かい寸法を抑えた配置計画を。
今現在、何もないところに建物が建つわけではなく、
既存のものを残すなど、注意する点が多くあり、
広い視野を持って進めなければと思うところです。
今後も建築士としてのノウハウを身につけていきます。
▲懐かしの恐竜遊具
(スタッフ:初瀬)