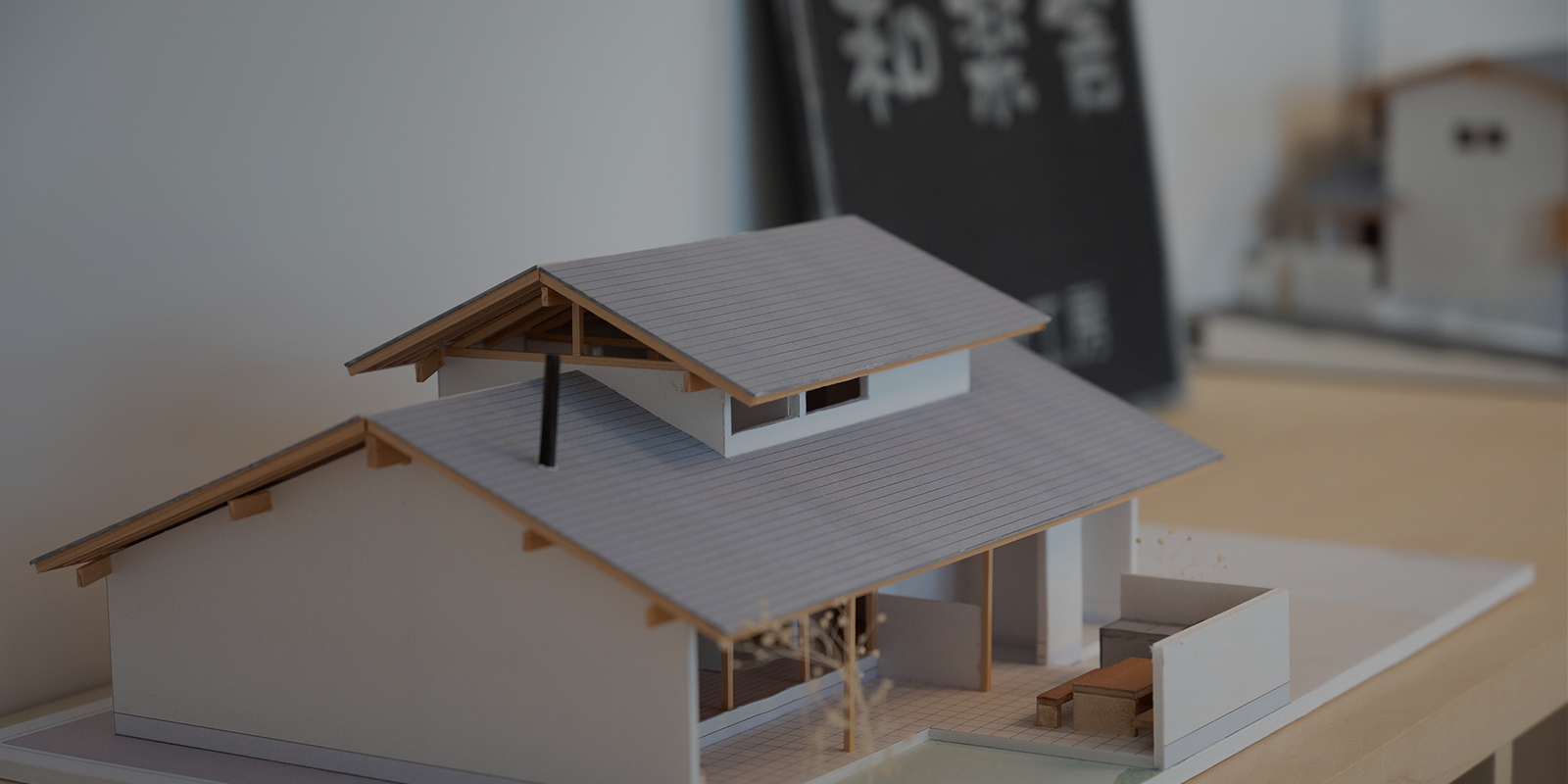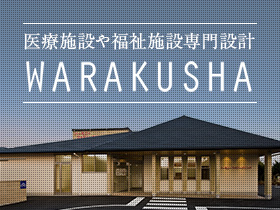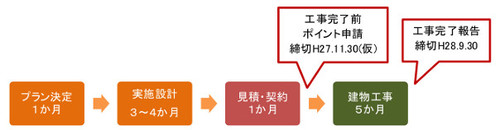和楽舎設計工房では、模型の写真を撮影する時に即席のスタジオが登場します。
背景が黒くなるように黒いフェルトの上に模型を載せ、
部屋を暗くしてLEDの照明スタンドで建物に陰影をつけます。
こちらは、建物のおおまかな形状を確認するための模型です。
影がつくことで形が分かりやすくなります。
こちらは、先ほどの建物の詳細の模型です。
壁の仕上材料を表現し、敷地に木も植えてることで
完成した時のイメージが掴みやすくなります。
こちらは別の模型ですが、
黒い背景があるとこんな感じですが
背景が無いと、
この様に建物の存在がすっかり薄れてしまいます。
住宅設計をした場合やその他の建物でも
模型を作成した時にはこちらの
即席の「和楽舎写真スタジオ」が登場します。
*************************
夢をかなえるお手伝い 住まいの設計パートナー
和楽舎 設計工房 山 崎 正 浩
浜松市東区小池町1363-1 小池ビル
Tel:053-466-0555 Fax:053-466-0558
*************************